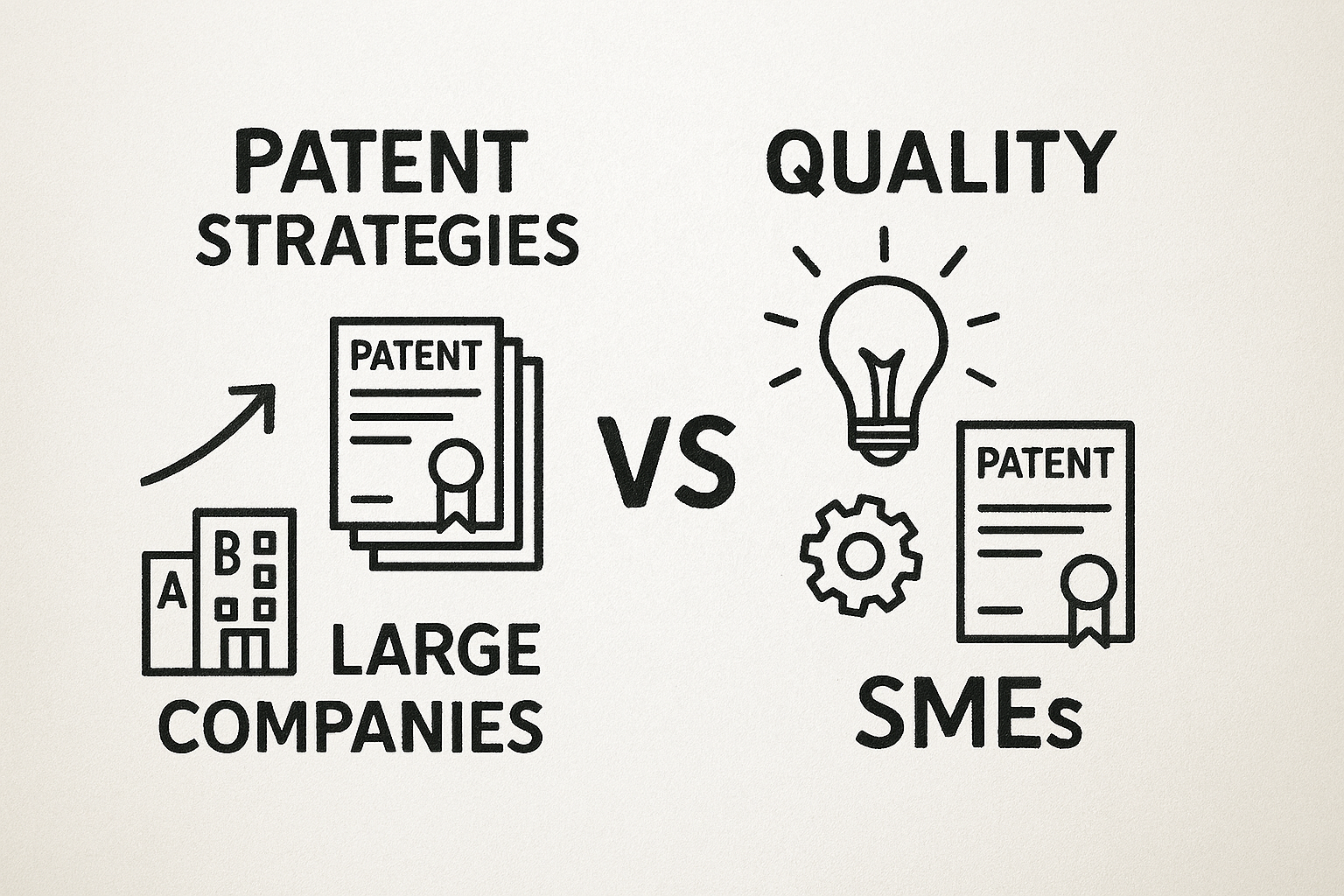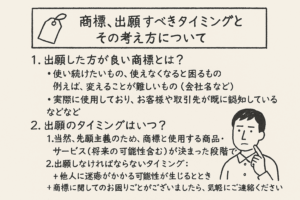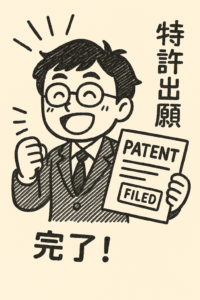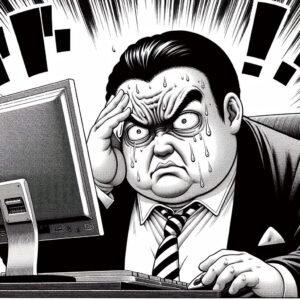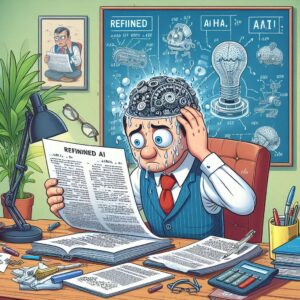IBMやマイクロソフトで知財戦略を推進して、業界全体に知財の重要性を浸透させた立役者であるマーシャル・フェルプスは、ライセンス交渉の際に提示する特許の数が25件を超える場合、相手方は抵抗せず交渉に応じる傾向にあると述べています。
確かに、大企業が豊富なリソースを活かして広範囲に特許を取得することで、市場を独占的に展開する戦略は現実的ですが、それに比して保有特許の数が少なくならざるを得ない中小企業にとって、特許取得は意味がないのでしょうか?
中小企業にとって有効な特許となる場合
25件程度の特許で他社の抵抗の意思をそぐ(≒他社の参入を防げる、又はライセンス収入を得られること)は、特定の技術領域を網羅的に保護するためには25件程度の特許が必要であるということです。
しかし、仮に「1件の特許」でも特に以下のような場合には、事業に有用なものとなり得ます。
- ニッチな技術領域での独自性が高い場合
- 製品のコア技術に関する特許である場合
- ライセンス収入を見込める技術である場合
また、中小企業が特許戦略を考える際は、以下のようなことがポイントとなります。
- 量より質:数を追うよりも、事業に直結する技術に絞って出願する。
- 地域性や市場性の考慮:地元密着型の技術やサービスにおいて特許による差別化が可能なことも。
- 費用対効果の検討:出願・維持費用に見合う価値があるかを見極める。
中小企業にとっての特許活用
上記のように特定の技術領域に絞った特許を取得することで、以下のような戦略的資産になり得ます。
1. 技術の差別化と信頼性の証明
特許取得=自社の技術が新規性・進歩性を満たしていることが特許庁によって認められたことになります。
これは、顧客や取引先に対して技術力の証明となり、信頼性を高めます。
2. 資金調達や提携の武器
特許は無形資産として評価されるため、ベンチャーキャピタルや金融機関からの資金調達、あるいは大企業との業務提携・ライセンス交渉において強力な交渉材料になります。
3. 模倣防止と競争優位の確保
中小企業はリソースが限られているため、模倣されるとすぐに競争力を失ってしまいます。
特許によって模倣を防ぎ、一定期間独占的に市場で展開できることは、事業の安定性に直結します。
4. 出口戦略(M&Aや事業売却)での価値向上
特許を持っていることで、企業の技術的価値が明確になり、買収対象としての魅力が増すことがあります。
特許ポートフォリオは、企業価値の一部として評価されます。
特許取得に関してご不明な点などございましたら、以下のお問合せからお気軽にご相談ください。